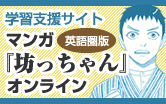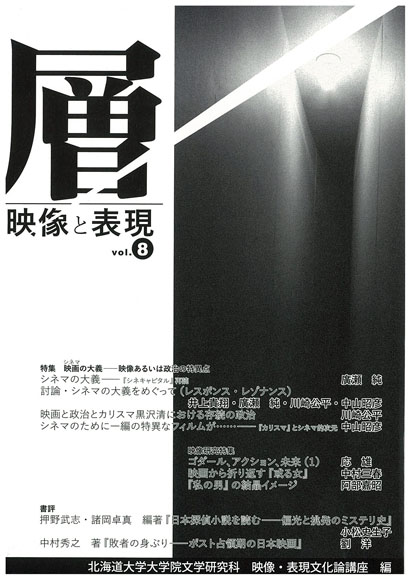
層 ―映像と表現
C3370
A5判並製
刊行年月 2007年06月
本書の内容
映画・写真・図像・マンガ・アニメ…。映像を手がかりに、社会的、文化的環境に関する諸問題を併せて究明。
近年、文化研究の場、特に若い世代のなかで映像や図像の地位が高まっています。そして、映画・写真・図像・マンガ・アニメなど映像に関わる事象を、日本・アジア・欧米の文化理論、思想史的研究、文学研究等と交錯させ、さらに映像と言語表現を取り巻く社会的、文化的環境に関する諸問題を併せて究明することのできる場が求められています。このような要望に応えるべく、従来の学問領域や枠組みにとらわれない、横断的な研究の発表媒体として、本誌『層』を創刊することとなりました。『層 ―映像と表現』というタイトルの「層」には、複数の領域の重なりという意味と、硬直化したアカデミズムに地殻変動を起すための裂け目といった意味が込められています。「映像批評の現在」という特集からスタートいたします。
層 ―映像と表現 創刊号 特集=映像批評の現在
刊行年月 2007年06月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-2359-5
創刊の辞 押野武志
●痙攣するイマージュ
―シュルレアリスムとイマージュについての覚書 齊藤哲也
●表面の劇 ―清水宏『有りがたうさん』をめぐって 川崎公平
●平面と微粒子 ―ヒッチコックにおける「顔」の問題 高野真理子
●張徹映画にみる運動 応 雄
●わたしのもとにやってくる亡霊 ―写真におけるメトニミーの作用 三浦なつみ
●主語のない強度について ―相米慎二の現代性(モデルニテ3) 浅野正道
【連載】
●離接と放射 ―小津安二郎〈と〉女優たち(1) 中山昭彦
●<啓蒙>の臨界 ―表象のリミット(1) 佐藤淳二
【小特集:メディア論の諸相】
●メディア論的文学論 ―声と文字の共犯性 押野武志
●探偵小説をめぐる問題系 ―『新青年』1921年前後 成田大典
●メロドラマと帝国 ―『君の名は』研究 横濱雄二
層 ―映像と表現 vol.2 特集=映画の後に来たるべきもの
刊行年月 2008年08月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-2935-1
【特集:映画の後に来たるべきもの】
●黒沢清と事後の光
―『LOFT』試論 川崎公平
●機械と運動・世界を変容するキートンのチェイス 長谷川功一
●シュルレアリスムの映画的条件
―あるいは映画ならざるもの 齊藤哲也
●ビデオゲーム/物語/テレプレゼンス 榊 祐一
【連載】
●離接と放射 ―小津安二郎〈と〉女優たち(2) 中山昭彦
●<啓蒙>の臨界 —表象のリミット(2) 佐藤淳二
【特集2:技法論の複数的展開】
●セシル・B・デミルの無声期初期監督作品における心理描写の技法的展開
檜山博士
●フレームの亀裂 ―ヒッチコックとエリセ 高野真理子
●自己の複数性 ―セルフ・ポートレートの主体をめぐって 三浦なつみ
●言語と図像の亀裂 —楳図かずお『洗礼』における<表層/深層>
小川 隆
●“指紋”と“血”―甲賀三郎「亡霊の指紋」を端緒に 井上貴翔
●炭鉱労働者と文化 ―1950年代における文学サークル運動を軸に(上)
水溜真由美
層 ―映像と表現 vol.3 特集1=暴力論の現在 特集2=映像理論を求めて――ドゥルーズ後
刊行年月 2010年01月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-3338-9
【特集1 暴力論の現在】
●怒りの日――人類学と許しえぬもの リュシアン・クレルク
●暴力とその禁止――「怒りの日」解説 櫻井典夫
●ブルトンとサド 齊藤哲也
●可視化の暴力――戦前期日本における指紋 井上貴翔
●「愛馬」と帝国――慰霊と名前をめぐる闘争 大川武司
●貨幣=女の生態学――太宰治「貨幣」論 花輪浩史
【連載】
〈啓蒙〉の臨界――表象のリミット(Ⅲ) 佐藤淳二
【特集2 映像理論を求めて――ドゥルーズ後】
●水の映画――ジャン・ヴィゴ、ジャン・ルノワール、費穆(上) 応雄
●断片と声――ブレッソン映画における「音の装置」 髙野真理子
●機械とモンタージュ――『ブリット』におけるカーチェイスの考察 長谷川功一
●〈面〉の混濁――クリント・イーストウッド『チェンジリング』論(上) 中山昭彦
●〈旅行中〉の言葉 Words on Travels――リービ英雄と多和田葉子 中村三春
●ねじれた推理――『かまいたちの夜×3』論 諸岡卓真
層 ―映像と表現 vol.4 小特集1=イメージの物質・亡霊・正義 小特集2=村上春樹の短編を読む
刊行年月 2011年03月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-3583-3
●小特集●イメージの物質・亡霊・正義
記憶喪失者のフラッシュバック —黒沢清『叫』における記憶・幽霊・イメージ(1) 川崎公平
写真と死 —写真における灰の経験 三浦なつみ
水の映画 —ジャン・ヴィゴ、ジャン・ルノワール、費穆(下) 応 雄
●連 載●
〈啓蒙〉の臨界(Ⅳ) —「人間学的循環」のめまい(1) 佐藤淳二
●小特集2●村上春樹の短編を読む
母娘関係の檻の中で —村上春樹「飛行機—あるいは彼はいかにして詩を読むようにひとりごとを言ったか」論 平野 葵
〈傷つきやすさ〉の変奏 —村上春樹の短編小説におけるヴァルネラビリティ 中村三春
売春と忘却―『君の名は』と『哀愁』との対比から 横濱雄二
内田百聞作品と知覚の変容―「大尉殺し」(一九二七) 山田桃子
押井守の戦後(史)表象と実在性―『鉄人28号』、『立喰師列伝』をめぐって 水川敬章
赤狩りとジョン・ヒューストンの作家的転換―フィルム・ノワール『キー・ラーゴ』論 長谷川功一
層 –映像と表現 vol.5
刊行年月 2012年04月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-3899-5
・絵画・映画・動画
◇力・ヒステリー・時間
―ドゥルーズのベーコン論をめぐって 髙野 真理子
◇出会いの準備
―黒沢清『叫』における記憶・幽霊・イメージ(2) 川崎 公平
◇動く水 ―宮崎駿における原形質性と可塑性 横濱 雄二
◇〈原作〉の記号学2
―溝口健二監督『雨月物語』の《複数原作》と《遡及原作》 中村 三春
◇動物への生成変化、およびその速度
―田壮壮の『狼災記』(二〇〇九)について 応 雄
・思想
◇〈啓蒙〉・「狂気」・歴史―デリダとフーコーをめぐるノート 佐藤 淳二
・文学
◇初期江戸川乱歩論―「一枚の切符」・「二銭銅貨」の射程 押野 武志
・研究ノート
◇戦中期における「映画国策」関係文献言説の特色 渡邉 大輔
層 –映像と表現 vol.6 小特集=生成する映画
刊行年月 2013年03月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-4196-4
●現象学の時空――内的時間意識と像意識 飛嶋隆信
【小特集】 生成する映画
●「女の子写真」と『OLの愛汁』――映像の換喩性をめぐって 阿部嘉昭
●戦後怪談映画と〈入れ替わる身体〉――中川信夫『憲兵と幽霊』における関係の重層 川崎公平
●悪女と機械――フリッツ・ラング『メトロポリス』におけるファム・ファタール表象について 長谷川功一
●日本におけるミステリとハードボイルド受容 押野武志
●村山知義「丹青」における〈朝鮮〉表象の多層性 韓然善
【連載】
●啓蒙論ノート(2)――彼女の倒錯者たちによって裸にされたジュリーさえも 佐藤淳二
●〈原作〉の記号学3――溝口健二『近松物語』と古典の近代化の問題 中村三春
【書 評】
●慎ましやかな革命の試み――長谷正人著『敗者たちの想像力―脚本家 山田太一』 劉洋
層 ―映像と表現 vol.7 特集1=映画研究の現在 特集2=文化における異郷
刊行年月 2014年03月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-4547-4
●ピエール・クロソウスキーにおける身体と交換―『歓待の掟』を中心として 松本潤一郎
【特集1 映画研究の現在】
●フレームを、フレームへと書き(描き)入れる―『なにもこわいことはない』 『愛、アムール』 阿部嘉昭
●『飾窓の女』におけるフロイトの夢思想の表象について 長谷川功一
●賈樟柯『世界』のメロドラマ的演出をめぐって 劉洋
【特集2 文化における異郷】
●異郷としての現在―小林秀雄「故郷を失つた文学」を起点として 中村三春
●<洲崎パラダイス>の消滅―戦後日本における赤線表象 押野武志
●会社員と独身者―伊井直行「さして重要でない一日」論 川崎 俊
【連載】
●啓蒙論ノート(3)―<表象>・「タブロー」・言語の起源 佐藤淳二
層 ―映像と表現 vol.8 特集=映画(シネマ)の大義―映像あるいは政治の特異点
刊行年月 2015年12月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-4973-1
【特集 映画(シネマ)の大義―映像あるいは政治の特異点】
●シネマの大義―『シネキャピタル』再読 廣瀬 純
●討論・シネマの大義をめぐって(レスポンス・レゾナンス) 井上貴翔・廣瀬純・川崎公平・中山昭彦
●映画と政治とカリスマ―黒沢清における存続の政治 川崎公平
●シネマのために一編の特異なフィルムが・・・・・・『カリスマ』とシネマ的次元 中山昭彦
【映画研究特集】
●ゴダール、アクション、未来(1) 応雄
●映画から折り返す『或る女』 中村三春
●『私の男』の結晶イメージ 阿部嘉昭
【書評】
●押野武志・諸岡卓真 編著 『日本探偵小説』を読む―偏光と挑発のミステリ史』 小松史生子
●中村秀之 著 『敗者の身ぶり―ポスト占領期の日本映画』 劉洋
層 ―映像と表現 vol.9 特集1=世界内戦と現代文学―創作と批評の交錯― 特集2=忍者と探偵が出会うとき
刊行年月 2016年10月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-5117-8
【特集1 世界内戦と現代文学―創作と批評の交錯―】
●三島由紀夫以後・中上健次以後・伊藤計劃以後 柳瀬善治
●「世界内戦」下、「伊藤計劃以後」のSFに何ができるか―仁木稔、樺山三英、宮内悠介、岡田剛、長谷敏司、八杉将司、山野浩一を貫く軸 岡和田 晃
●実作の立場から見るユートピア文学 仁木 稔
●世界内戦と「わたし」たち 樺山三英
●複数の「世界内戦」に向けて 押野武志
【特集2 忍者と探偵が出会うとき】
●忍者から探偵へ/過渡期のロマンを検証する―山田風太郎『警視庁草紙』を手がかりに 谷口 基
●少女マンガに引き継がれた忍者表象―和田慎二『スケバン刑事』の戦略 小松史生子
●「日常の謎」と隠密―瀬川コウ『謎好き乙女と奪われた青春』論 諸岡卓真
●堀田善衞『広場の孤独』論―二〇世紀における政治と知識人 水溜真由美
●映画の犬―『ホワイト・ドッグ』『シーヴァス』をめぐって 阿部嘉昭
●意想外なものの権利―今井正監督の文芸映画『山びこ学校』と『夜の鼓』 中村三春
【書評】
●木下千花著『溝口健二論―映画の美学と政治学』 川崎公平
層 ―映像と表現 vol.10 特集1=SFの再定義 特集2=映画論の諸相
刊行年月 2018年02月
定価1,980円
(本体1,800円)
ISBN978-4-8433-5342-4
【特集1 SFの再定義】
●二十一世紀のニューウェーブ――J・Gバラードの初期短編に見る時間論 藤元 登四郎
●ブラックホール/M(マインド)・E(イーター)/忌字禍(イマジカ)――フィクションのサイエンスとしてのSF 金沢 英之
●飛浩隆の享楽 石和 義之
●「(コン)パッション」の表象可能性あるいは「来るべき未来の病」に罹患した「凡人」たちとは誰か――現代SFを題材として考える 柳瀬 善治
【特集2 映画論の諸相】
●感情イメージの「発生的エレメント」――「顔=クロースアップ」から「任意空間」へ 応 雄
●死の超克としてのサクリファイス――タルコフスキーが描く死と再生 忍澤 勉
●「延長」による悲劇――『ミスティック・リバー』について 中井 朋美
●増村保造と巫女としての女優――映画『刺青(いれずみ)』における谷崎潤一郎『刺青』のテーマの再構成について 長谷川 功一
●孤立する顔――万田邦敏『接吻』について 阿部 嘉昭
(自由論文)
●団地の文学史 樺山 三英
●アクシデント性=動物性、そして「サーガなきサーガ」へ――伊井直行「草のかんむり」論 川崎 俊
●日本におけるサブカルチャーをめぐる語りの諸類型 榊 祐一
【研究ノート】
●〈愛されない〉ということ――村上春樹「品川猿」など 中村 三春
【書評】
●中村秀之著『特攻隊映画の系譜学――敗戦日本の哀悼劇』 劉 洋