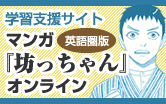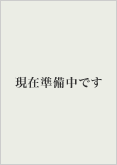
学習院大学図書館所蔵
丹鶴城旧蔵幕府史料 全35巻
揃定価929,500円(揃本体845,000円)
ISBN 978-4-8433-2761-6 C3321
B5判上製/函入
刊行年月 2010年11月
本書の内容
江戸幕府の政治を具体的に伝える、紀州徳川家付家老水野忠央(ただなか)収集の貴重な史料群。久々の新出に値する幕府史料。
※このページ上部の「刊行年月」は、第4回配本の刊行年月を表示しています。
刊行にあたって 松尾美惠子(学習院女子大学教授)
学習院大学図書館所蔵「旧丹鶴城蔵書幕府書類」は、紀州徳川家の付家老で、紀伊国新宮城(丹鶴城)主の水野忠央が収集した史料群の一部である。水野忠央の蔵書といえば、弘化四年(一八四七)から嘉永六年(一八五三)にかけて刊行された古典籍の叢書「丹鶴叢書」が著名であるが、彼の集めたものは書籍ばかりではない。あまり知られていないが、江戸幕府の諸記録類も多数収集している。国立国会図書館蔵「新宮城書蔵目録」(全一〇冊)の第七冊目の目録に収蔵されているものがそれに当たる。各題名を見ると興味深いものが多い。現在ではその殆どが所在不明であるが、幸いにもその一部が学習院大学図書館に伝来した。
学習院所蔵の史料は「御老中留書類」の内の日常政務・儀礼関係が中心で、いずれも近世史研究者にとって垂涎の史料ばかりである。このほか、奏者番の部局日記と思われる享保・元文期の「幕府日記」や対外関係の史料も注目に値する。
水野忠央は文化面での業績のほか、紀州藩政を主導し、井伊直弼と図って藩主徳川慶福(家茂)を十四代将軍とするなど、政治的にも活動した人物として知られるが、幕府中枢の記録類を借覧し、書写することができたのは、そうした忠央の地位、威権によるところが大きかったであろう。しかし桜田門外の変後、隠居を命じられ、新宮に居を移し、慶応元年(一八六五)に没した。彼が集めた書籍類は江戸から新宮城に運ばれ、保管された。
それがどのような経緯で散逸したか明らかではないが、学習院がその一部を入手したのは明治二十年(一八八七)頃らしい。昭和初年の『学習院図書館和漢図書目録』には「旧丹鶴城蔵書幕府書類」としてその書目が載せられている。近年、学習院大学の「学術資料・文書等の管理と有効利用の在り方調査プロジェクト」(代表者高埜利彦教授)により、同史料の調査が行われ、その結果、「丹鶴城旧蔵幕府史料」が、国立公文書館内閣文庫や、国立国会図書館、東京都公文書館にもない極めて貴重な史料群であることが判明した。
幕府の史料は幕末維新の動乱、その後の火災等によりその多くは失われたが、この度、学習院大学図書館の許可を得、調査に参加した院生諸氏の協力を得て、新出の史料を学界に提供できることになった。本書の公刊が日本近世史研究、とくに幕政史・制度史・幕藩関係史・武家社会史の一層の進展に寄与することになれば幸いである。
【推薦文】
江戸幕府政務処理の実態 藤田 覚(東京大学教授)
水野忠央といえば丹鶴叢書だが、それ以外に居城の紀伊新宮城(丹鶴城)に膨大な書籍、記録類を収集し所蔵していたらしい。多くは散逸したが、幸いなことに江戸幕府の諸記録の一部が学習院大学図書館に伝存するという。私は、うかつにもまったく知らなかった。
このたび、幕政史研究の権威である松尾美惠子氏を監修者として、その幕府関係史料が『丹鶴城旧蔵幕府史料』として刊行されることになった。老中らが政務を処理するうえで必要な先例や規定、大名らからの問い合わせと返答の書留など、江戸幕府の日常的な政務処理の実態をよく伝える史料が含まれ、江戸幕府の政治のありかた、政務処理の仕組みを具体的に解明するうえで大変に貴重な史料群である。さらに、江戸幕府の中枢と深く関わった水野ならではというべき、これまで知られていなかった幕末対外関係史の重要な史料も含まれていて、幕末政治史研究のためにも新たに貴重な史料を提供している。『丹鶴城旧蔵幕府史料』は、江戸時代政治史研究の新たな発展に重要な貢献をすることになるだろう。広く近世史研究に活用されることを期待し、本書を推薦したい。
興味つきせぬ史料集 深井雅海(國學院大學栃木短期大学教授)
松尾美惠子氏の監修により、学習院大学図書館所蔵の「旧丹鶴城蔵書幕府書類」が、四期に分けて刊行されることになった。この史料は、紀州徳川家の付家老であった水野忠央が収集した史料群の一部であるが、目録の題名を見ると、興味をひかれるものが多い。それもそのはず、老中御用部屋の記録類を書写したものであるという。
なかでも、さまざまな問題や事件についての経過と処断を記した「例格類聚」、諸大名から老中に提出された伺いに対する回答をまとめた「内意留」、老中の合議内容を分類した「類聚録」などは、老中を中心とする政治システムの解明に有益と思われ、また奏者番による江戸城内の日記とみられる「幕府日記」は、殿中儀礼の仕組みを明らかにするうえで大きな役割を果たしそうである。
いずれにしても、本史料集が幕政史・幕府制度史・幕藩関係史などの進展に大きく寄与するものと確信し、お薦めする次第である。
水野忠央と丹鶴城
水野忠央(みずの ただなか 一八一四~一八六五、文化十一~慶応元)は、幕末の紀州藩付家老であり、自ら居城を持つ新宮城主であった(新宮城はまたの名を丹鶴城)。嘉永二年(一八四九)に主君の徳川慶福が紀州藩主となると、後見役となり藩政の実権を握り、さらに妹が十二代将軍徳川家慶の側室であったことから、幕政にも発言力を強め、安政五年(一八五八)には、井伊直弼と組み、藩主の慶福を第十四代将軍(家茂)とした。有職故実・古典文学に造詣が深く、数万点の典籍を校訂させ刊行した「丹鶴叢書」で知られる一方、進取の気性に富み、洋式船の建造や洋式軍隊の編成なども行った。吉田松陰は「水野奸にして才あり、世すこぶるこれを畏る……また一時の豪なり」と評したという。
※付家老 幕府が御三家等の監督のために遣わした家老。尾張・紀伊・水戸の御三家で「五家」あった。大名並の待遇が付与され、代々世襲。明治元年新宮藩(三万五千石)が成立し、水野氏は藩主となった。
【本書の特徴】
●幕府政治の具体像を提供する史料
故実、旧慣、先例が重んじられる幕府政治では、老中が政務を処理するうえで、先例の書留、大名からの問い合わせと返答の書留などは、当時必要な具体的資料であった。今回刊行する、新宮城(丹鶴城)主水野忠央が残した史料は、まさにそれらの、幕府中枢の記録類を写させたものである。
●国立国会図書館、国立公文書館内閣文庫等にもない貴重な史料群
幕末維新の動乱で多くの幕府史料は失われたが、水野家、学習院大学図書館と大切に保存されてきた、今回刊行する史料は、久々の新出に値する幕府史料の刊行である。
●充実した解説
各史料ごとの書誌的事項は勿論、必要に応じた細目一覧(本文頁と対応)を含めた充実した解説を収録。
●悉皆刊行
今回水野忠央が書き写させた「老中留書類」を原本の配列順そのままに悉皆刊行する中で、「丹鶴叢書」も含め、水野忠央研究の一助となることを願った。
●利用者の便宜に配慮した印刷・編集
本書は、「旧丹鶴城蔵書幕府書類」をすべて新たに撮影し、虫損・破損で読みにくい箇所は、写真複製の方法を採り、「内意留」のように、朱筆がある場合は、朱筆を「*」で示し、「幕府日記」などには、柱に年月日をたてるなど、鮮明で使いやすい史料提供に努めた。
学習院大学図書館所蔵 丹鶴城旧蔵幕府史料 第1回配本 全6巻
刊行年月 2007年12月
揃定価201,300円
(揃本体183,000円)
ISBN978-4-8433-2762-3 C3321
B5判上製/函入
【主な収録内容】
「丹鶴城旧蔵幕府書目録」
学習院大学図書館所蔵「旧丹鶴城蔵書幕府書類」三〇〇冊の目録。水野家が手放した際に作成されたものと考えられている。
「幕府日記」
奏者番による幕府日記。享保十八年七月~元文三年十一月まで、いくつかの部分に欠如がみられるが、三九冊が現存する。徳川吉宗時代の江戸城内の儀礼や出来事が、詳細な情報で記されている。加えて、奏者番内における業務記録と思われる記事も多見される。個人の手留ではなく役職での部局日記とみられるが、いわゆる「幕府日記」としての体裁もうかがえる、非常に興味深い史料である。
「例格類聚」
江戸幕府の老中が政務の参考にした先例集。幕府儀礼に関する問題やその他の事件について、個別具体的な事例ごとに見出しを付けて、発端・経過と最終的な幕府の処断を記す。享保~安永年間にかけての事例を収録。
「類聚録」
老中同士で申し合わせたことについて、内容別に書き付けたもの。年代は、天明期から天保期のものを所収している。内容は多岐に渡り、「両丸江御入之部」、「御参詣之部」、「御成之部」などの項目を立て内容を分類し、年代順に記載している。老中が職務遂行に際して参照した、先例集の類のものと言えよう。
「類例秘録」
代官・領主からの問い合わせに対する幕府の回答をまとめたもの。記事内容の年代は安永~天保年間。巻之一~巻之八は、主に幕領代官あるいは預所役人の支配領域内の各種事件の吟味伺いに対する勘定奉行の回答、巻之九・巻之十は、主に大名・旗本領での寺社に関わる問題への寺社奉行の回答を載せる。
「内意留」
諸大名より老中に出された内意伺いを書き留めたもの。また、その処理についても朱で簡潔に記す。天保五年三月~同十四年九月までのものを所収するが、数ヶ月~一年単位で部分的に欠落部分がある。記録者について明確な記載はないが、記載年代が水野忠邦の本丸老中在職期間とほぼ一致することから、水野家で作成されたものと推測される。
「御用召 御内書 御奉書」
大名の登城や大名の家来の呼び出しを中心にまとめる。また、それに対する返信も記載している。ここで言う御内書とは、御内書渡しのための呼び出しについて記しているもので、一般的に言う御礼献上に対する返礼そのものは載せていない。御奉書も、呼び出しの奉書である。年代順には配列されていないが、文政十三年から安政四年のものを所収し、嘉永・安政年間の記録が大半である。
「日光御社参之記」
天保十四年に行なわれた、十二代将軍家慶の日光社参に関する記録。日にちが欠落している部分もあるが、天保十三・十四年の記事を記載する。ただし、社参の期間中は将軍の動静についての記述はなく、留守の記事が掲載されている点が特徴的である。作成者については明記されていない。
「謁差出」
御三家家老から幕府老中へ差し出された書付をまとめたもので、天保十四年正月から五月までを所収している。後半部分には「天保十四年卯年證文裏判」と題される史料が収められており、一位様(家斉室寔子)等の合力金請取りを中心に書き留めている。また、幕府役人の拝借金請取りの記録も若干ながら含む。
「御規定伺」
大名家からの質問に対する幕府の回答を書き留めたもの。記事は享保期から安政期に及ぶ。主に御城使(留守居役)から、用頼と思われる幕府役人へ問い合わせている。質問内容は「罪科之心得」、「御小人目付勤方」「妹之跡江姉縁付」「御成之節心得」など、多岐にわたる。
「被仰出留」
幕府よりの仰出を書き留めたもの。仰出の内容とともに、担当者・伝達場所・列座の者なども記載する。年代は天保八年のみ。内容は多岐に渡り、目次の分類によると「御名代 御使 上使」や「御広鋪」など、計二一項目を立てる。老中の職務遂行上の参考とするために作成されたものであろう。
丹鶴城旧蔵幕府史料 第1巻 丹鶴城旧蔵 幕府書目録/幕府日記1
刊行年月 2007年12月
定価35,200円
(本体32,000円)
ISBN978-4-8433-2763-0
丹鶴城旧蔵幕府史料 第2巻 丹鶴城旧蔵 幕府日記2
刊行年月 2007年12月
定価36,300円
(本体33,000円)
ISBN978-4-8433-2764-7
丹鶴城旧蔵幕府史料 第3巻 丹鶴城旧蔵 例格類聚/類聚録/類例秘録
刊行年月 2007年12月
定価39,600円
(本体36,000円)
ISBN978-4-8433-2765-4
丹鶴城旧蔵幕府史料 第4巻 丹鶴城旧蔵 内意留1
刊行年月 2007年12月
定価30,800円
(本体28,000円)
ISBN978-4-8433-2766-1
丹鶴城旧蔵幕府史料 第5巻 丹鶴城旧蔵 内意留2
刊行年月 2007年12月
定価30,800円
(本体28,000円)
ISBN978-4-8433-2767-8
丹鶴城旧蔵幕府史料 第6巻 丹鶴城旧蔵 御用召 御内書 御奉書/日光御社参之記/謁差出/御規定伺/被仰出留
刊行年月 2007年12月
定価28,600円
(本体26,000円)
ISBN978-4-8433-2768-5
学習院大学図書館所蔵 丹鶴城旧蔵幕府史料 第2回配本 全9巻
刊行年月 2008年12月
揃定価216,700円
(揃本体197,000円)
ISBN978-4-8433-3065-4 C3321
B5判上製/函入
【主な収録史料】
「寺社・参詣・立寄・墓参届伺之部」
主に寺社・信仰・祭祀に係わる事例、約一四〇件を書き留めたもの。弘化・嘉永期を中心に収録されている。諸大名が老中・寺社奉行へ提出した伺書・問合書・願書・届書が大半を占め、内容は寺社およびそこに属する者の取り扱いに関するもの、寺社参詣および大名家の祭祀に関するもの、公家との交際に関するもの等が見られる。
「呈書・勤方・参勤・御暇」
御用番等に対して大名から提出された、表題の案件に関する内慮伺い等の文書の控えである。天保十四年頃から安政三年頃までのものを所収する。願書類には例書なども引かれ、事務的な経過も大まかではあるが記録している。また、付札や書取・挨拶などによる回答も記載されている。なお、願書などの提出に関しては「頼」の先手などの役人の情報も記す。
「出奔・久離・追放」
大名・旗本から町奉行所に提出された届出、あるいは問い合わせの記録。内容は、家来やその親族の出奔・久離・追放の扱いについての報告や伺い、久離帳への記載または帳消といった処理に関するものである。記事は寛政四年から安政三年のものが記載されているが、とくに弘化・嘉永期のものが中心となっており、町奉行所からの返答を記した付札や下札も書き写されている。
「江戸絵図新規出来御用諸達届留」
文化六年に作成した江戸絵図が四十年たって老朽化したため、新規に江戸絵図を作成したときの関連書類をまとめたもの。嘉永五年、「掛り下奉行」の作成。内容は、新規江戸絵図の制作のために居屋敷周辺の状況を取り調べるよう諸大名・諸役人に達したものの写や、調書の取り方に関する諸大名・諸役人から作事奉行への伺が主となっている。幕府による江戸絵図作成の内容を詳細に記す史料で、絵図作成にかかった費用の内訳も含む。
「礼献式」
諸大名が、家督・隠居・元服・初而御目見・任官・婚姻などのライフイベントに際して、幕府に対して行った御礼献上の品目・数量を、大名家ごとに記し、あわせて先例の年月日を網羅的にまとめた典礼書。御礼献上という儀礼を通して、それぞれの大名・大名家の家格と幕藩体制における位置づけが一覧できると同時に、幕府が大名をどのように序列づけて統制していたかを物語る。天保期の写本と推定。
「官省便覧」
寺社奉行が各機関に宛て発給した文書と、それに対する回答をまとめた記録。江戸町奉行・勘定奉行との間で交わされた裁判・評定所に関する記録のほか、寺社奉行が管轄していた寺院僧侶・神社神職や紅葉山役人の動向など多岐にわたる内容を含む。寛政四年から文政七年の文書を収録。
「縁組問合」
婚姻・養子などの縁組に関する問い合わせや報告、およびその回答の記録で、目付や御用番等に宛てて提出されたものが大半を占めている。寛政五年から嘉永五年の約百三十件について所収している。縁組だけでなく、離縁・再縁の事例も見受けられ、幕府の縁組規定の細部がうかがわれる史料である。
「忌服・服穢」
目付や御用番等に宛て、主に大名から提出された忌服や病欠に関する伺いや届出の記録。弘化・嘉永期を中心に、文化二年から安政四年のものを所収する。過去の事例を引いているものもあり、また、その後の経過を記録しているものもある。幕府における穢意識とそれへの対処などが垣間見られる史料と言えよう。
「自火在府類焼有無之部」
大名の上・下屋敷、抱屋敷から発生した火事の記録。延焼の有無により分類されている。火事の報告はただちに火元の大名から幕府老中になされたが、類焼が無ければその旨を明記し、類焼があれば差控の伺いを同時に提出することになっていた。伺いに対する幕府の回答は付札をもってなされた。その一連の経過がこの史料から判明する。内容年代は享保期より文化・文政期に及ぶ。
「屋鋪之部」
大名の上・中・下屋敷・抱屋敷に関する願いや届とその回答を記録したもの。四巻の内三巻目を欠く。一・二は弘化年間、四は嘉永・安政年間が中心。内容は多岐にわたるが、相対替願いをはじめ、屋敷内の火の見櫓や長屋、表(裏)門・番所の設置、修復に関する記事が豊富。また自家が覗かれるとして、隣接する町家の二階の窓を塞がせた次第や花火が屋敷内に落下した報告も見え、江戸の武家屋敷の生活空間をかいまみることができる。
「天保七申年十月諸御用留并諸願」
大名や幕府の役人などが幕府へ提出した願・届を到着順にまとめたもの。「天保七申年諸御用留十月上之部」と「天保七申年十月諸御用向留下」の2冊からなる。「上之部」には願、「下」には届がそれぞれ収録されているが、「下」の巻末には「縁組願」など届以外のものも含まれる。その内容は職務にかかる経費を願うものや、洪水被害の届出など多岐にわたる。
丹鶴城旧蔵幕府史料 第7巻 一紙目録・当日奉書/一紙目録・奉書・当日奉書/寺社・参詣・立寄・墓参届伺之部
刊行年月 2008年12月
定価17,600円
(本体16,000円)
ISBN978-4-8433-3066-1
丹鶴城旧蔵幕府史料 第8巻 呈書・勤向・参勤・御暇/参勤〈御礼前・早参府〉部/類聚録(補遺)
刊行年月 2008年12月
定価25,300円
(本体23,000円)
ISBN978-4-8433-3067-8
丹鶴城旧蔵幕府史料 第9巻 天保七申六月奉書留/雑々集/出奔・久離・追放/雑・人別証文
刊行年月 2008年12月
定価22,000円
(本体20,000円)
ISBN978-4-8433-3068-5
丹鶴城旧蔵幕府史料 第10巻 年表/江戸絵図新規出来御用諸達届留
刊行年月 2008年12月
定価25,300円
(本体23,000円)
ISBN978-4-8433-3069-2
丹鶴城旧蔵幕府史料 第11巻 礼献式(1~4)
刊行年月 2008年12月
定価18,700円
(本体17,000円)
ISBN978-4-8433-3070-8
丹鶴城旧蔵幕府史料 第12巻 礼献式(5~8)/官省便覧
刊行年月 2008年12月
定価27,500円
(本体25,000円)
ISBN978-4-8433-3071-5
丹鶴城旧蔵幕府史料 第13巻 隠居・家督・御目見・養子・養女/前髪・半髮・名改・袖留・惣髪/親類書認振/縁組問合/婚礼之部上
刊行年月 2008年12月
定価24,200円
(本体22,000円)
ISBN978-4-8433-3072-2
丹鶴城旧蔵幕府史料 第14巻 出生・丈夫・実名所判・出家・修験/忌服・服穢/火事要覧/自火在府類焼有無之部
刊行年月 2008年12月
定価27,500円
(本体25,000円)
ISBN978-4-8433-3073-9
丹鶴城旧蔵幕府史料 第15巻 諸伺/御用留 取扱鈴木半十郎/天保七申年十月諸御用留并諸願 上/天保七申年十月諸御用留并諸願 下/諸御用留/城詰米・国役金・囲米・高役金伺/屋鋪之部
刊行年月 2008年12月
定価28,600円
(本体26,000円)
ISBN978-4-8433-3074-6
学習院大学図書館所蔵 丹鶴城旧蔵幕府史料 第3回配本 全10巻
刊行年月 2009年12月
揃定価217,800円
(揃本体198,000円)
ISBN978-4-8433-3267-2 C3321
B5判上製
【主な収録内容】
「天保十二年十一月来翰留」
御三家や大名、寺社等から老中宛に出された書状をまとめたもの。水野忠邦のもとへの到着日順に編纂されており、天保十二年十一月一日から十六日までに到来した約三百件を所収する。内容は将軍家の慶弔時や増上寺等への参詣に際してのご機嫌伺い、献上にともなう書状が多数を占める。水野は当月の月番老中でもあり、老中奉書・返札が発給される過程を検討するための一助となろう。
「文政十一年 書抜」
奏者番による記録をもとにして、各テーマごとに時系列で編集されたもの。所収する年代は文政十一年のみ。内容は奏者番の業務日誌のような性格のものであり、本文ではその日その日の行事等を簡潔に記している。ただし、まれに記事の後に「追而」書が記されている場合があり、そこでは本文に関する注記や備忘的な記事、奏者番内での決済事項等が記録されており、奏者番の業務運営を知る上で興味深い史料であると言えよう。
「天保九年 書抜」
奏者番による記録をもとにして、各テーマごとに時系列で編集されたもの。所収する年代は天保九年のみ。内容・様式共に「文政十一年 書抜」と同様であるが、天保九年分の全てが残存しているわけではなく、百以上あると推定される項目立てのうち、七十二番目?八十八番目までの部分のみが三巻に仕立てられたものである。ただし、「文政十一年 書抜」と同様に、奏者番の業務運営を知る上で興味深い史料であることには変わりはない。
「沼津様書付留書抜」
使者や名代・書付等によって、御三家御三卿、諸大名らから老中の元に届けられた内容を書き留めたもの。所収する年代は、文政元年十一月より天保五年正月まで。様式としては、書状そのものを写したものではなく、あくまで内容を簡潔に記したものである。史料の内容は、上使派遣、病気見舞い等に対する返礼や御台様へのお礼等で、老中奉書等に対する返礼に近いものが多いがそれに止まらない。史料名の「沼津」は水野忠成を指していると考えられ、水野忠成方の史料を書き写したものであると推測される。
「御守殿方留」
十一代将軍徳川家斉の長女淑姫の担当となった若年寄による、姫君付人とのやりとりを記録した御用留。御守殿とは、将軍息女が御三家・御三卿などに嫁いだのちの敬称、また、その生活する建物をさす。「御守殿方留」の年代は文化三年(一八〇六)十月から文化十三年(一八一六)十二月晦日までで、淑姫が尾張家十代徳川斉朝に嫁いだのちの付け人の動きや、将軍家族としての淑姫の儀礼参加状況、将軍御立寄などにおける幕府との連携の様子がうかがえる。
「御守殿諸書付留」
「御守殿方留」から諸種の達・触の写のみを抜き出して、おおむね一年ごとに分類収録したもの。付人の役替・褒賞をはじめとして、淑姫や将軍家斉の行動に伴う通達などがまとめられている。年代は文化三年(一八〇六)十月から、淑姫が死去する文化十四年(一八一六)まで。第十一巻には淑姫の葬儀にかかわる通達や、その後の付人の処遇、御守殿の解体の報告などが記載されている。
「御関所証文伺」
諸大名から幕府に対して出された関所の通過や手形の発給に関する伺・問合・届・願などと、それらに対する幕府(老中・留守居など)の対応の記録。女性の関所通過(出女)と、武器の輸送(入り鉄砲)に関する案件が多数を占める。天保・弘化・嘉永年間を中心に、約一五〇件の事例を収録。
「寺社奉行勤役中取扱留」
寺社奉行が扱った文書を関係する役職群ごとに分類した記録。本来複数冊で構成されていたとみられるが、本書はそのうちの一冊(同役・支配ノ分・両奉行を収録)である。寺社奉行が発給した文書を中心に書き留められている。なお、特定の個人の留書ではなく、文化年間に寺社奉行を勤めた大久保忠真や阿部正精ら複数人の記録から編集したものと考えられる。
「内桜田御番所置帳書抜并御成例書」
将軍の御成の際の、内桜田門番の任務についてまとめたもの。「宝暦五年乙亥二月内桜田御番所置帳書抜御成 例書」と「明和二年乙酉六月内桜田御番所勤格御成一件」の二つからなる。前者には御成の際の番所警備において、当番が病欠した場合の対応などが先例を用いてまとめられている。また、後者には門番が提出する請書の雛形などが御成の経路ごとに収められており、御成の側面から当時の門番の職務について窺わせる好史料であるといえよう。
丹鶴城旧蔵幕府史料 第16巻 天保十二年十一月来翰留/文政十一年書抜1
刊行年月 2009年12月
定価19,800円
(本体18,000円)
ISBN978-4-8433-3268-9
丹鶴城旧蔵幕府史料 第17巻 文政十一年書抜2
刊行年月 2009年12月
定価20,900円
(本体19,000円)
ISBN978-4-8433-3269-6
丹鶴城旧蔵幕府史料 第18巻 文政十一年書抜3・天保九年書抜
刊行年月 2009年12月
定価22,000円
(本体20,000円)
ISBN978-4-8433-3270-2
丹鶴城旧蔵幕府史料 第19巻 沼津様書付留書抜/扣目録
刊行年月 2009年12月
定価25,300円
(本体23,000円)
ISBN978-4-8433-3271-9
丹鶴城旧蔵幕府史料 第20巻 御守殿方留1
刊行年月 2009年12月
定価26,400円
(本体24,000円)
ISBN978-4-8433-3272-6
丹鶴城旧蔵幕府史料 第21巻 御守殿方留2
刊行年月 2009年12月
定価22,000円
(本体20,000円)
ISBN978-4-8433-3273-3
丹鶴城旧蔵幕府史料 第22巻 御守殿方留3
刊行年月 2009年12月
定価22,000円
(本体20,000円)
ISBN978-4-8433-3274-0
丹鶴城旧蔵幕府史料 第23巻 御守殿諸書付留1
刊行年月 2009年12月
定価17,600円
(本体16,000円)
ISBN978-4-8433-3275-7
丹鶴城旧蔵幕府史料 第24巻 御守殿諸書付留2/御守殿御省略帳面扣
刊行年月 2009年12月
定価22,000円
(本体20,000円)
ISBN978-4-8433-3276-4
丹鶴城旧蔵幕府史料 第25巻 御関所証文伺/寺社奉行勤役中取扱留/桜田御番所置帳書抜并御成例書
刊行年月 2009年12月
定価19,800円
(本体18,000円)
ISBN978-4-8433-3277-1
学習院大学図書館所蔵 丹鶴城旧蔵幕府史料 第4回配本 全10巻
刊行年月 2010年11月
揃定価293,700円
(揃本体267,000円)
ISBN978-4-8433-3510-9
B5判上製
【主な収録内容】
「御沙汰書附御用触」〈「殿中御礼書留」「殿中御沙汰並御礼留」「御沙汰書」とも〉
(第26~29巻所収)
本史料は、江戸城中において、大規模な儀礼や人事情報等、城内全体に日々伝達された御沙汰書の記録である。その内容は、老中・若年寄等の執務場所である御用部屋で作成された日記の内容とほぼ一致するとされる。また、部分的ではあるが、天保二年から元治元年までの殿中御沙汰書を所収する。特に元治元年分については、同年に出された御触書も同時に所収しており、江戸城内における平常の動きを知る上で好適な史料と言えよう。
「地方雑記」(第30巻所収)
江戸幕府代官の地方支配における勤務のマニュアルにあたる史料。「勤要集」あるいは「地方雑記」という題で多くの代官所で作成されたといわれる。享保期以降の代官やその役人にとっては勤務上必須の事項が収録されている。『地方凡例録』収載の「勤要集」とは異本である。
「京都巡見記」(第30巻所収)
文政三年頃、職務として京都を巡見した者の手控えとみられる。東福寺筋・高尾筋・吉田筋など、十四日分の記録がある。巡見先は目録にあげられただけでも約百四十ケ所。寺社がほとんどであるが、中には鷹ケ峯御薬園・西陣織殿・御茶壺蔵等もある。巡見先の基礎的な情報のほか、そこで見聞きしたことや感想など、記述は詳細である。
「仏蘭西国条約并税則/亜墨利加国条約並税則/魯西亜国条約并税則/英吉利国条約并税則/阿蘭陀国条約并税則」(第31巻所収)
安政五箇国条約とも呼ばれる、安政五(一八五八)年六月~九月にかけて、幕府がアメリカ・オランダ・ロシア・イギリス・フランスと結んだ修好通商条約と税則(貿易章程)を所収する。これらの条約内容はすでに広く知られているところではあるが、本史料では各巻末に「安政六未年従老職被渡書付六月十一日巳」などの記載が見られる点が特徴的であるといえよう。
「珍説見聞集」(第32~34巻所収)
信濃国筑摩郡赤木村(諏訪藩領)の人、丸山久治郎(仁右衛門)が、自分の身に起こった出来事を軸に、近隣の事件、諸国の珍談・奇談を書き綴ったもの。記事の年代は文化二(一八〇五)年~文政六(一八二三)年、文政八(一八二五)年~天保八(一八三七)年、嘉永二(一八四九)年~嘉永四(一八五一)年。著者は天保九(一八三八)年江戸に出て、錦魚屋となっているが、同年より十年間の記事を欠く。前半生は百姓、後半生は町人として過ごした一庶民の個人史としても興味深い史料である。
「公紀私録」(第34巻所収)
和歌山藩付家老の水野忠央が幕閣や藩政とどのように関わったのか、その動向を知りうる貴重な史料。和歌山・新宮の風聞探索書をはじめ付家老同士の書状も含まれ、和歌山藩政史だけではなく幕藩関係史を研究するうえでも有効な新出史料である。
「進達談済写」(第35巻所収)
和歌山藩の御用人・町奉行・寺社奉行・勘定奉行・御仕入方などからの進達書(上申書)をまとめた新出の和歌山藩関係文書。嘉永五・六年を中心として、国許の町方・寺社行政および藩財政の一端などを知りうる貴重な藩政史料。
丹鶴城旧蔵幕府史料 第26巻 御沙汰書附御用触1
刊行年月 2010年11月
定価27,500円
(本体25,000円)
ISBN978-4-8433-3478-2
丹鶴城旧蔵幕府史料 第27巻 御沙汰書附御用触2
刊行年月 2010年11月
定価25,300円
(本体23,000円)
ISBN978-4-8433-3479-9
丹鶴城旧蔵幕府史料 第28巻 御沙汰書附御用触3
刊行年月 2010年11月
定価27,500円
(本体25,000円)
ISBN978-4-8433-3480-5
丹鶴城旧蔵幕府史料 第29巻 御沙汰書附御用触4
刊行年月 2010年11月
定価23,100円
(本体21,000円)
ISBN978-4-8433-3481-2
丹鶴城旧蔵幕府史料 第30巻 検知一件、地方雑記、郡国提要、京都巡見記ほか
刊行年月 2010年11月
定価36,300円
(本体33,000円)
ISBN978-4-8433-3482-9
丹鶴城旧蔵幕府史料 第31巻 安政五箇国条約、海防備論、別段風説書ほか
刊行年月 2010年11月
定価16,500円
(本体15,000円)
ISBN978-4-8433-3483-6
丹鶴城旧蔵幕府史料 第32巻 珍説見聞集1
刊行年月 2010年11月
定価34,100円
(本体31,000円)
ISBN978-4-8433-3484-3
丹鶴城旧蔵幕府史料 第33巻 珍説見聞集2
刊行年月 2010年11月
定価38,500円
(本体35,000円)
ISBN978-4-8433-3485-0
丹鶴城旧蔵幕府史料 第34巻 珍説見聞集3
刊行年月 2010年11月
定価31,900円
(本体29,000円)
ISBN978-4-8433-3486-7
丹鶴城旧蔵幕府史料 第35巻 進達談済写、公紀私記録ほか
刊行年月 2010年11月
定価33,000円
(本体30,000円)
ISBN978-4-8433-3487-4