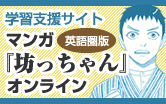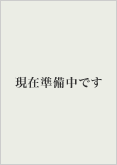
洋々社談 全4巻
揃定価74,800円(揃本体68,000円)
ISBN 978-4-8433-2382-3 C3321
A5判
刊行年月 2007年04月
本書の内容
明治初期(明治8年4月~明治16年3月)の学術結社「洋々社」の機関誌である『洋々社談』創刊号から終刊95号までを復刻出版。近世と近代の学術・知識集団を考察する上で、大変重要な史料。
『洋々社談』は、明六社やその啓蒙思想を再検討するために欠くことができない雑誌である。西村茂樹、依田学海、大槻文彦、黒川真頼、南部義籌、大川通久、飯島半十郎など、和漢洋、人文・自然科学の当時の学界の最先端にあった人々が加わっており、明治政府の教育、文化行政との関係も注目される。
【本書の特色】
●明治近代化を支えた、学術・知識集団を考察する上で、大変重要な史料である。
●明治初期の学界の最先端にあった人々の業績が収録されている。
代表的論文以下の通り。
大槻文彦「日本文法論」、黒川真頼「言語文字改革の弁」、南部義籌「無事ヲ改換スル疑」同「以羅馬字写国語並盛正則漢学論」、大川通久の地理、測量関係の論文、飯島半十郎「日本全国面積表」「沿海地図凡例」等
洋々社談 第一巻
刊行年月 2007年04月
定価18,700円
(本体17,000円)
ISBN978-4-8433-2390-8 C3321
A5判
【目次より】
第一号 明治八年四月九日
洋々社記 大槻盤翁 九
文会演説 阪谷素 一〇
小言四則 西村茂樹 一二
ものまなひにつきてのうれたみごと 黒川真頼 一四
擬奉英国女帝書 大槻文彦 一七
技由妙悟説 那珂通高 二〇
化石谷説 榊原芳野 二一
気燈説 小永井八郎 二三
第二号
支那字ノ数 木村正辞 二九
言語文字改革説ノ弁 黒川真頼 三一
細川春流吊野矢翁文 那珂通高 三二
ペルリ日本記行中ノ訳文一節 大槻文彦 三四
記奥鉱洋傭 小永井八郎 三八
地租改正論 南部義籌 三九
第三号
地租改正論ノ続 南部義籌 四七
西暦沿革略説 西村茂樹 五二
小学教授書につきての論 黒川真頼 五六
洋学ノ疑 依田百川 五七
水品略 榊原芳野 六〇
第四号
読米国政体略説訳本 阪谷素 六五
富国ノ基礎ハ私有ヲ保護スルニアル論 南部義籌 六七
与外姪貞子書 榊原芳野 六九
西語雑録一 西村茂樹 七一
陸中国鹿角郡説 那珂通高 七四
読支那字説 小永井八郎 七九
擬連珠 野口之布 七九
第五号 官許 明治八年九月
豊臣太閤略譜 黒川真頼 八五
反正天皇ノ崩年 木村正辞 八七
_工ヲ記ス 阪谷素 八九
仏家拝像説 平野知秋 九二
義所鳥山君墓誌銘 那珂通高 九二
善言無価 飯島半十郎 九五
弁文明国多盗賊 野口之布 九七
博覧余稿 大槻磐翁 九七
第六号 官許 明治八年一〇月
木内宗五郎上徳川家綱公書 西村茂樹 一〇五
俗伝実ヲ失フ話 依田百川 一一〇
忍説 阪谷素 一一三
熱ノ説 大井鎌吉 一一五
鴒ヲシテ音信ヲ達スルノ説 木村正辞 一一七
第七号 官許 明治八年一一月
日本文法論第一 大槻文彦 一二五
文字ヲ改換スル議 南部義籌 一二八
脩国語論、文字ヲ改換スル議ノ附録 一三三
書天津撃英兵事後 小永井八郎 一三五
柳沢吉保侯略譜 那珂通高 一三六
第八号 官許 明治八年一〇月
白河楽翁公ノ遺事 依田百川 一四五
三百年前ノ職人ノ雇料 黒川真頼 一四七
火星光輝ノ問 平野知秋 一四八
幸福人詩 西村茂樹 一四九
海泥ニ鰍の談 榊原芳野 一五〇
古川古松軒遺事 阪谷素 一五一
弓削道鏡ヲ皇胤トスル説 木村正辞 一五四
古今仏寺大教 附支那仏寺大数 那珂通高 一五六
第九号 明治八年一二月
人口論 西村茂樹 一六五
古昔ノ人口ノ数 木村正辞 一七〇
山本左左衛門伝 小永井八郎 一七二
近稿二首 大槻磐翁 一七四
貴族ヲ論ス 依田百川 一七六
第一〇号 明治九年一月
新年会演説 阪谷素 一八五
我国風人体の歌、仮字の違ひしにあらず 榊原芳野 一九〇
論足利義政求典籍宝貨千明 黒川真頼 一九一
雑話 飯島半十郎 一九三
梅見に行たる記 木村正辞 一九四
記西人善舟 小永井八郎 一九七
普魯士大王弗勒徳力第二世徳行 室岡峻徳 一九八
第一一号 明治九年二月
人口論附説 西村茂樹 二〇七
俚言出拠 那珂通高 二一二
木内宗五郎事蹟 平野知秋 二一六
第一二号 明治九年三月
足利尊氏治世風俗 黒川真頼 二二五
記蟋蟀盆 小永井八郎 二二七
畢司馬略(ビスマルク)伝 西村茂樹 二二七
名君賢相喜人謗己説 那珂通高 二三五
本邦文物開化ハ聖徳太子ニ創始スルヲ論ス 依田百川 二三七
第一三号 明治九年四月
戞利巴底(ガリバルディ)略伝 西村茂樹 二四三
魯西亜ニテ荘僕ヲ廃シタル話 南部義籌 二四九
古今米価 那珂通高 二五二
借金利子ノ貴キ古モ其例アル証 依田百川 二五六
力士谷風伝 大槻磐翁 二五九
第一四号 明治九年四月
西語雑録二 西村茂樹 二六五
授文法須自卑説 那珂通高 二六七
植物史 木綿舶来 榊原芳野 二七〇
書注南有伝後 小永井八郎 二七一
墨水看桜小引 依田百川 二七二
哥子哈堅(コルツハゲン)至考ノ記 室岡峻徳 二七三
第一五号
印刷術ノ史 大槻文彦 二七九
旋雲筒 西村茂樹 二八五
動物史中金魚 榊原芳野 二八八
植物史中あちさゐ 同 二八九
務一事説 埴原経徳 二九〇
化学者ノ試験 大井鎌吉 二九一
第一六号 明治九年六月
新田義負朝臣贈官考 黒川真頼 二九七
古今寿踰百歳者 那珂通高 二九九
記鍜工事 飯島半十郎 三〇三
木中弾丸記 平野知秋 三〇四
養生論 大槻文彦 三〇六
明暦慶安ノ町触 木村正辞 三〇九
第一七号 明治九年七月
地学大意一 西村茂樹 三一五
田舎人の話 那珂通高 三一八
秦漢以前君ノ間後世ト同シカラサルヲ論ス 依田百川 三一九
故幕府新選隊士近藤昌宜土方義豊碑 大槻磐翁 三二二
武烈天皇崩年ノ聖算 小中村清矩 三二七
第一八号 明治九年七月
諸国ノ童謡俚歌 那珂通高 三三三
捕狐者藤兵衛伝 小永井岳 三三九
前田慶次郎自賛 阪谷素(坂谷)三四一
織田信長公亡骸埋葬説 小中村清矩 三四三
第一九号 明治九年八月
長短説 西村茂樹 三五一
谷風伝補遺、附近世躯幹長大者 那珂通高 三五四
楽水亭記 依田百川 三五八
豊臣秀頼 木村正辞 三六〇
日本(ニッポン)「ジャパン」正訛ノ弁 大槻文彦 三六二
第二〇号 明治九年八月 官許 明治八年一二月
上古墳墓考 黒川真頼 三六九
大田六助伝 島田重礼 三七三
堪忍ノ喩 阪谷素 三七五
太神楽起原及角兵衛獅子ノ称 那珂通高 三八二
第二一号 明治九年九月
亜力伯(アルプス)山の雪の危難 西村茂樹 三九一
上古墳墓考二 黒川真頼 三九六
古代ノ文字 那珂通世 四〇一
記鼬鼠 依田百川 四〇四
泥炭説 飯島半十郎 四〇四
第二二号 明治九年一〇月
東洋印刷術ノ史 大槻文彦 四〇九
記匠人 小永井八郎 四一六
算盤起原 那珂通高 四一六
銭を択るおきてのうつりかはり 大沢清臣 四一九
古今文字ノ沿革 那珂通世 四二七
第二三号 明治九年一一月二〇日
雑話 飯島半十郎 四三四
東京ノ地名、附蝦夷地名 西村茂樹 四三六
俵字義 那珂通高 四三九
第二四号 明治九年一二月二六日
総追捕使という職 黒川真頼 四四五
南亜弗利加の獅 西村茂樹 四四七
琵琶法師 那珂通高 四五一
第二五号 明治九年一二月二九日
記所聞 那珂通高 四六一
南亜弗利加ノ獅ノ続 西村茂樹 四六六
後征西将軍考 依田百川 四七〇
洋々社談 第ニ巻
刊行年月 2007年04月
定価18,700円
(本体17,000円)
ISBN978-4-8433-2391-5 C3321
A5判
【目次より】
第二六号 明治一〇年一月二九日
長慶院御譲位といふは浮説なりといふ弁 黒川真頼 七
日本ノ四大島 那珂通世 九
男女同権説 西村茂樹 一二
伊達正宗ガ遣欧使ノ記事 大槻文彦 一五
烈公遺話 青山勇 一九
第二七号 明治一〇年三月一〇日
サクラハ櫻桃ニシテ櫻桃ハユスラニ非サルノ弁 伊藤圭介 二五
石田治部少輔実名ノ訓 林昇 二七
萬歳及厄払考 那珂通高 二八
押字私印ノ沿革 小中村清矩 三三
獅子舞説補考 榊原芳野 三八
第二八号 明治一〇年三月三一日
豊公収兵器於民間告諭 那珂通高 四三
清人ノ詩数首 伊藤圭介 四六
門松並ニ節分ノ撒豆 小中村清矩 四八
植物史・櫟 榊原芳埜 五一
網魚乃考附_ 同 五二
朱学伝来 平野知秋 五四
第二九号 明治一〇年四月三〇日
蚊並蚤ノ説 伊藤圭介 六一
地震説 西村茂樹 六五
足利義満将軍南帝に善く事奉りし考 依田百川 七〇
諭言五則 那珂通高 七三
日本全国面積表 飯島半十郎 七四
第三〇号 明治一〇年五月三一日
転生ノ説 那珂通世 七九
天皇の御名の沿革考 黒川真頼 八六
祭亡_陸軍中尉貞文 依田百川 八九
安徳天皇其他ノ旧跡 小中村清矩 九一
目安箱ノ始末 増田贊 九三
第三一号 明治一〇年六月三〇日
足利氏の代学問の廃れたりし事を記す 那珂通高 一〇一
食虫其他異食ノ説 伊藤圭介 一〇七
寛政年間処刑人ノ数 増田贊 一一三
第三二号 明治一〇年八月二日
神世ノ伝易理ニ似タルノ疑 那珂通高 一一九
植物中、茶ニ代ヘ飲用スベキ諸品 伊藤圭介 一二五
阿波国徳島人富助に与へて砂糖製造を勧る書 榊原芳野 一二六
上世ノ物価 小中村清矩 一二九
第三三号 明治一〇年八月三一日
金一両の重さの事 黒川真頼 一三七
救荒食物便覧 伊藤圭介 一四〇
祭故内閣顧問木戸松菊公文 依田百川 一四五
勲位ノ説 木村正辞 一四六
第三四号 明治一〇年九月二六日
軽気球(一) 西村茂樹 一五五
九月十三夜 那珂通高 一五八
救荒食物便覧(続) 伊藤圭介 一六四
山椒魚 附人魚ニ三種アル事 木村正辞 一六六
第三五号 明治一〇年一〇月三一日
社談会集の記 小中村清矩 一七三
釈尊興廃 平野知秋 一七六
春夏秋冬説 西村茂樹 一七八
軍中の二話 依田百川 一八〇
倭文読法 那珂通高 一八四
短歌 一八五
清少納言枕草子首章 一八六
第三六号 明治一〇年一一月三〇日
桐布説 伊藤圭介 一九〇
薄荷護謨樹之説 同 一九三
春夏秋冬説ノ評 南部義籌 一九五
利息 増田贊 一九七
君主ヲ称スル語、各国相似タルノ考 大槻文彦 二〇三
第三七号 明治一〇年一二月二五日
隅田川梅若塚説 平野知秋 二〇九
我カ邦古今旅況ノ別 那珂通高 二一一
渡九頭龍川記 西村茂樹 二一四
日本植物図説序 伊藤圭介 二一六
鶏姦 木村正辞 二一九
書籍ノ数 同 二二〇
第三八号 明治一一年一月二六日
上古年代考 那珂通世 二二七
維新以前ノ攘夷ヲ唱フル者ヲ論ス 依田百川 二三六
演劇実伝 那珂通高 二三八
第三九号 明治一一年二月二八日
下関海峡ノ戦 西村茂樹 二四五
佐藤直方閨門隠微説 平野知秋 二五二
閨門隠微説 佐藤直方 二五三
処刑ノ遺骸ヲ別用ト為スノ説 増田贊 二五五
向日葵説 伊藤圭介 二五七
第四〇号 明治一一年三月二六日
志〔し〕つのをたまき 那珂通高 二六三
姓名沿革ノ概略 小中村清矩 二六八
隕石略記 室岡峻徳 二七二
楠正成卿の子孫と称するもの永録年間朝廷に仕へし話 依田百川 二七五
第四一号 明治一一年四月二九日
点図角筆擬唐俗説 那珂通高 二八五
沢瀉ハ毒草ノ説 伊藤圭介 二八七
妬忌説 西村茂樹 二八九
織田氏の王室を尊崇せしハ信長の時に始りしに非さる説 依田百川 二九一
大尺小尺呉服尺の説 大沢清臣 二九二
猿楽考 小中村清矩 二九四
第四二号 明治一一年五月二四日
本邦上古ヨリ銅ノアリケル事 黒川真頼 三〇三
乱舞ノ説 平野知秋 三〇五
鳥頭毒説 伊藤圭介 三〇八
軽気毬(ニ) 西村茂樹 三一三
第四三号 明治一一年六月二九日
最温の衣服 西村茂樹 三二一
清人詩(社談第二十八号続) 伊藤圭介 三二四
俳優の伎もまた学問の一端たる説俳優市川団十郎に示す 依田百川 三二五
慣用熟語出於仏経及漢籍者 那珂通高 三二八
外教伝来略記 室岡峻徳 三三二
第四四号 明治一一年七月三一日
着眼ノ力 西村茂樹 三三九
珊瑚島、即チ微細ノ植虫聚合堆積シテ一大島ヲ築成スルノ奇説 伊藤圭介 三四二
東大寺南大門ノ狛犬ノ事 黒川真頼 三四九
言語、容飾 飯島半十郎 三五〇
第四五号 明治一一年八月三一日
竹島松島ノ記事 大槻文彦 三五七
亜力伯(アルプス)山の雪の危難(二) 西村茂樹 三六三
浮島ノ話 伊藤圭介 三六六
浮島附考 那珂通高 三六八
第四六号 明治一一年八月三〇日 (※九月か)
足利氏南帝の御裔に厚かりし事 依田百川 三七五
一男配数婦記 西村茂樹 三七六
伝姆江島俳優生島新五郎等ト淫通ノ所決申渡書 増田贊 三八二
紀事二則 平野知秋 三八五
第四七号 明治一一年一〇月三一日
中古病人ヲ棄ル弊風並施薬院悲田院 小中村清矩 三九三
後亀山天皇の太上天皇尊号のこと 依田百川 三九九
植物漢名新考 伊藤圭介 四〇一
独逸皇太子夫妻の行状 室岡峻徳 四〇三
第四八号 明治一一年一一月三〇日
足利氏の時の武家役の事 黒川真頼 四一一
水天宮考 小中村清矩 四一二
植物漢名新考 伊藤圭介 四一五
西暦ノ二月二十八日ノ私考 平野知秋 四一七
南部家所蔵天正年間毀城始末古文書写 那珂通高 四二〇
第四九号 明治一一年一二月二八日
我邦称日本起原 那珂通高 四二九
赤松満祐将軍義教を殺せしとの考異 依田百川 四三一
満天星説 伊藤圭介 四三三
谷中延命院住持死刑申渡書 増田贊 四三四
拝礼考 小中村清矩 四三七
洋々社談 第三巻
刊行年月 2007年04月
定価18,700円
(本体17,000円)
ISBN978-4-8433-2392-2 C3321
A5判
【目次より】
第五〇号 明治一二年一月二八日
太陰暦ニ用ヰシ十二時ノ事 木村正辞 七
英国人民ノ等級 西村茂樹 九
明人記我風土者 那珂通高 一四
夷三郎之説 榊原芳野 一五
水仙説 伊藤圭介 一八
梟示ノ始廃 増田贊 二〇
第五一号 明治一二年二月二八日
歌垣踏歌 小中村清矩 三一
穀木二神考上編 那珂通高 三四
喫肉説 木村正辞 四一
第五二号 明治一二年三月三一日
徳川孝恭公薨去話 平野知秋 四九
府下高低表 大川通久 五二
朝鮮国出陣ノ訴状 木村正辞 五八
第五三号 明治一二年四月二七日
_猴奇談 伊藤圭介 六七
西国の天の古説 西村伯翁 七二 (茂樹)
方今欧米屈指ノ人傑ハ皆老人ナルノ説 三橋淳 七六
続楠正成卿の子孫と称するもの永録年間朝廷に仕へし話 増田贊 七九
第五四号 明治一二年五月二〇日
西国理学ノ源流 西村伯翁 八五
奇事三条 木村正辞 八九
友人手簡 那珂通高遺稿 九二
第五五号 明治一二年六月二一日
軽気球(三) 西村伯翁 一〇五
用の字の活 榊原芳野 一〇八
樒シキミ説 伊藤圭介 一一〇
新造溶鉱炉記 那珂通高遺稿 一一三
続梟示ノ始廃 増田贊 一一五
祭那珂梧楼先生文及詩歌 依田百川、西村茂樹、小中村清矩 一一七
桜賦 平野知秋 一一八
第五六号 明治一二年七月一二日
毛利元就か陶全薑を討ぜしとき詔書を請奉りしといふ誤 依田百川 一二三
水神考下編 那珂通高遺稿 一二五
馬利亜提列撤(マリアテレサ)略伝 大井鎌吉 一二九
琉球ノ武備 大槻文彦 一三一
樺皮説並哭那珂通高君詩 伊藤圭介 一三四
第五七号 明治一二年八月二五日
葵の弁 附録楓(カツラ) 榊原芳野 一三九
磐渓大槻先生墓表 中村正直 一四四
佐倉城ノ沿革 平野知秋 一四五
俗語の根拠 小中村清矩 一五一
第五八号 明治一二年一〇月一日
足利氏明使を接遇せし礼節 依田百川 一五九
俗語の根拠 前号ノ続キ 小中村清矩 一六二
棣棠花説 伊藤圭介 一六六
日本人口惣(ママ)計考 黒川真頼 一七〇
第五九号 明治一二年一〇月三一日
日本人口総計考(前号ノ続キ) 黒川真頼 一七七
西国理学ノ源流(二) 西村伯翁 一八一
楠公義兵を挙げたる時の戦 太平記の脱誤 依田百川 一八五
以羅馬字写国語並盛正則漢学論 南部義籌 一八八
第六〇号 明治一二年一一月二九日
日本人口惣計考(前号ノ続キ) 黒川真頼 一九五
以羅馬字写国語並盛正則漢学論(前号ノ続キ) 南部義籌 一九八
水戸景山公ノ逸事 小山朝弘 二〇一
徳川氏の時規制厳なりしも中世ハかくハ無りしこと 依田百川 二〇三
木曾山中(詩) 伊藤圭介 二〇五
近年古墳墓ノ発掘最モ多シ 増田射水 二〇六
天皇ハ皇帝ト称ス可ラザルノ弁 平野知秋 二〇七
第六一号 明治一二年一二月二七日
相馬大作の事を論す 依田百川 二一七
文章博士紀伝博士考 小中村清矩 二二〇
天皇ヲ皇帝トモ称シ奉ルヘキ事 依田百川、小中村清矩 二二六
社談傍評三則 埴原経徳 二三〇
第六二号 明治一三年二月二日
先生ト呼ブノ濫叨ナル事 小山春山 二三五
儒書ノ読法 平野知秋 二三七
浪打峠を越る記 青森紀行の内 西村伯翁 二三九
景山公逸事ヲ読ム 平野知秋 二四三
日本紀ヲ読ムニハ心スヘキ事 小中村清矩 二四六
第六三号 明治一三年三月四日
虎狩 西村伯翁 二五三
東河伊能翁小伝 大川通久 二五七
高橋東岡先生小伝 大川通久 二六一
徳川氏の末世捕盗の小吏奸を為せし事 依田百川 二六二
木菴伽羅笠記 伊藤圭介 二六五
綱吉将軍時有傷狗而死者 増田射水 二六八
第六四号 明治一三年四月七日
北条義時廻船式目 大槻文彦 二七三
研堂緒方先生碑 阪谷素 二七八 (坂谷)
一月寺愛_神谷転(カミヤウタタ)の事の為め寺社奉行に上る書の後に書す 増田射水 二八一
近代三盗 西村伯翁 二八三
第六五号 明治一三年五月一日
北条義時廻船式目(前号ノ続) 大槻文彦 二九一
伝馬町、獄舎ノ記事 小山春山 二九五
平田篤胤が貧困に屈せざりし話 依田百川 二九八
樒ノ中ニ事リシ話 平野知秋 三〇二
神国ノ称 小中村清矩 三〇四
第六六号 明治一三年五月二五日
中山大納言愛親卿関東下向ありて閑院宮尊号の事を議論せられしことの弁 依田百川 三〇九
近代三盗の話 西村伯翁 三一六
劣れる者ハ見わけやすく勝れたる者は見わけがたし 埴原経徳 三二〇
徳川氏ノ出版条例 大槻文彦 三二二
第六七号 明治一三年六月二八日
越後粟生島記事 大川通久 三二七
櫻桃説 伊藤圭介 三三〇
石出常軒の事 小山春山 三三二
南北講話の後七十八年にして猶南朝の皇胤復讐を謀る者ありしこと 依田百川 三三六
明文類抄序 平野知秋 三四〇
響尾蛇の毒 西村伯翁 三四一
第六八号 明治一三年八月四日
我国諸山ノ高低 大川通久 三四五
一事によりて当時の人情好尚を察すへき説 依田百川 三五二
近代三盗の続 西村伯翁 三五五
第六九号 明治一三年九月一五日
西国上古ヨリ量地術ノアリシ説 大川通久 三六三
大学寮釈奠古礼ヲ講習スル事 平野知秋 三六五
古医道三翁ノ雑話 伊藤圭介 三七一
第七〇号 明治一三年一一月一日
書籍ノ災厄 木村正辞 三七九
御廻リ之名 増田射水 三八一
冨士山説 平野知秋 三八二
薩藩歴代之詩 伊藤圭介 三八七
今ノ人力車ヨリ前人力車アリ 増田射水 三九〇
第七一号 明治一三年一二月九日
豊太閤ノ船法 大槻文彦 三九九
釈迦ノ生卒年月 西村伯翁 四〇四
明の楊文聡が山水の画を秘蔵せし話 依田百川 四〇八
残る菊の香 小中村清矩 四一〇
洋々社談 第四巻
刊行年月 2007年04月
定価18,700円
(本体17,000円)
ISBN978-4-8433-2393-9 C3321
A5判
【目次より】
第七二号 明治一四年二月一九日
鈴木藤吉郎小倉庵長治伝 大槻文彦 七
俗画師歌川貞秀の言を記す 依田百川 一〇
俳優の言と雖も取るべきものあり 依田百川 一二
華盛頓新聞紙ノ抄訳 飯島半十郎 一五
第七三号 明治一四年三月一五日
古代の小歌並後世の俚歌 小中村清矩 二五
犬公方ノ事 大槻文彦 三一
高橋作左衛門渡辺登等ノ刑罸申渡書 大川通久 三五
第七四号 明治一四年四月二〇日
島津義弘の手簡を読み豊臣太閤よく豪傑を駕御するの術を知る 依田百川 四三
磔刑ハ西洋より入りしといふ説 大槻文彦 四七
沿海地図凡例 飯島半十郎 五〇
第七五号 明治一四年五月二〇日
古瓦叢談 伊藤圭介 六一
中野石翁墨水の別業に住して奢侈のふるまひありし話 依田百川 六三
謡曲の説 小中村清矩 六六
諸子百家ノ言西哲ノ論ト暗合スルノ説 井上哲次郎 七二
書江芸閣吸月楼扁後 平野知秋 七四
書遊撃将軍張国英書画扇背 飯島半十郎 七五
第七六号 明治一四年六月三〇日
白川少将楽翁公が幕府の諸臣に示諭せし書の評 依田百川 七九
蒲生君平家系 小山朝弘 八二
荒井白石を祭る時霊代の前に申す詞 小中村清矩 八七
蜜蜂熟地に移りて蜜醸さぬ話 大槻文彦 九一
徳川氏ノ末年財政困難ナリシ話 飯島半十郎 九二
哭朗盧阪谷翁 増田贊 九四
第七七号 明治一四年七月三〇日
種痘ノ始 西村伯翁 九七
聞見随筆 依田百川 九九
古人取法於天地論 井上哲次郎 一〇四
愛猫ノ説 木村正辞 一〇九
揮毫ノ統計 大井鎌吉 一一一
遺戒経後 平野知秋 一一二
第七八号 明治一四年七月二五日 (※八月か)
伊井直孝が裂きしといふ伊達政宗が百万石墨付現存する事 大槻文彦 一一五
日本書紀ヲ読ム心得 木村正辞 一二三
古処山樵ノ詩 井上哲次郎 一二八
第七九号 明治一四年九月三〇日
古瓦叢談(前号続) 伊藤圭介 一三三
伊達政宗百万石墨付の話(前号の続き) 大槻文彦 一三八
学庭叢語第一 井上哲次郎 一四一
教と学との訓義 小中村清矩 一四五
第八〇号 明治一四年一〇月三一日
日光男体山へ登るの記 大槻文彦 一五一
見聞随筆の二 依田百川 一五九
両羽諸鉱山発見ノ年代 大川通久 一六三
黄檗僧徒の書画 飯島半十郎 一六五
第八一号 明治一四年一一月三〇日
古医道三翁雑話続 伊藤圭介 一七五
曲亭馬琴か著述及ひ吾仏(アカホトケ)の記、後(ノチ)の為(タメ)の記事、並天保年間民間の小説を禁ぜられし事 依田百川 一八一
学庭叢語第二 井上哲次郎 一八七
第八二号 明治一四年一二月二五日
見聞随筆 前号の続 依田百川 一九五
新に造れる長_亭にて社会を催す詞 小中村清矩 一九七
奥州街道ノ高低 大川通久 二〇〇
長崎丸山ノ娼妓フミ和蘭ニ到リシ話 飯島半十郎 二〇四
第八三号 明治一五年二月五日
気候の人身に感する説 西村伯翁 二一五
騙盗寺僧を欺きて大金を得たる話 依田百川 二一九
モチヰルといふ和語の活用 大槻文彦 二二三
政宗百万墨付余考 大槻文彦 二二九
第八四号 明治一五年二月二八日
白河楽翁公猿楽の伎を評せられし話並木賊刈の能の事 依田百川 二三五
雑説 飯島半十郎 二三七
閨の梅か香 小中村清矩 二三八
清三朝親選書目 西村伯翁 二四三
尺度之事 大川通久 二四六
第八五号 明治一五年三月二九日
亜力伯(アルプス)山の雪の危難(三) 西村伯翁 二五五
自堕落先生の狂文章 依田百川 二五八
学庭叢話第三 井上哲次郎 二六三
尺度之事(前号ノ続) 大川通久 二六八
第八六号 明治一五年四月三〇日
文章論 小中村清矩 二七五
物徂徠先生の履歴 依田百川 二八〇
清三朝親選書目(前号ノ続) 西村伯翁 二八七
第八七号 明治一五年五月三一日
下総国に正学を唱へし士自殺せし話 依田百川 二九五
世ニ多ク伝ハラサル詩 井上哲次郎 二九九
大食会之事 飯島半十郎 三〇三
阿部重次殉死ノ実記 大川通久 三〇六
第八八号 明治一五年七月三一日
歌舞伎はなし 小中村清矩 三一五
封建時代の訴訟 依田百川 三二二
慶安殉死の補遺 西村伯翁 三二五
袖萩用韻倣梁陳体 井上哲次郎 三二九
第八九号 明治一五年八月三一日
燈謎詩 西村伯翁 三三五
封建時代の訴訟 前号の補遺 依田百川 三三九
瀛海篇ノ抄録並ニ其評 井上哲次郎 三四二
けしからぬ、けしかるのこと 岡敬孝 三四八
第九〇号 明治一五年九月三〇日
喜馬拉山(ヒマラヤ)ノ記 西村伯翁 三五五
番椒図説 伊藤圭介 三六一
金瘡に灸する術 黒川真頼 三六五
朝鮮近事詩 依田百川 三六七
晃山湯瀑記 大槻文彦 三六八
第九一号 明治一五年一〇月三〇日
喜馬拉山ノ記(前号ノ続) 西村伯翁 三七九
見聞随筆(前号の続) 依田百川 三八三
番椒図説(続) 伊藤圭介 三八六
廻船問屋並印形組合人数 宮崎道三郎 三九二
第九二号 明治一五年一一月三〇日
書会沢吉成二氏遺文後 青山勇 三九九
雑論 吉成南園 四〇〇
時務策 会沢憩斎 四〇一
日本国地図測量ノコト 大川通久 四一〇
左府橘公木像記 大槻文彦 四一三
第九三号 明治一五年一二月三〇日
藤田東湖の書翰、幕府講武所を建られし時これを論せしもの 依田百川 四一九
桑斯克立(サンスクリット)ヲ論スル書簡 西村伯翁 四三〇
第九四号 明治一六年一月三〇日
蓑衣鶴図説 伊藤圭介 四三九
蜀山翁が掌記にのする話 依田百川 四四二
妾を切捨たる届並に忌服伺の書 岡敬孝 四四八
第九五号 明治一六年三月三〇日
千代萩政岡の実伝 大槻文彦 四五九
喜馬拉山記(九十一号ノ続) 西村伯翁 四六六
頼山陽の手簡 依田百川 四七〇
賢女の文 埴原経徳 四七四