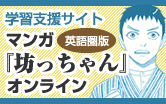HOME > 書籍検索 > 社史で見る日本経済史 第7期 > 社史で見る日本経済史 第7期 第3回 全3巻【new!】 > 社史で見る日本経済史 第7期 第114巻 三木金物誌
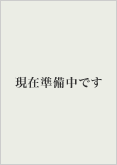
社史で見る日本経済史 第7期 第114巻 三木金物誌
定価30,800円(本体28,000円)
ISBN 978-4-8433-7151-0 C3321
刊行年月 2025年11月
オンライン書店
オンライン書店で『社史で見る日本経済史 第7期 第114巻 三木金物誌』の情報をチェックする
本書の内容
(小西勝治郎編著、三木金物誌刊行会刊、1953年)
三木金物は播州(兵庫県)三木を特産地とする19世紀初頭から現在に至る200年以上にわたる、手づくりの技や先進機器の技術と良質の素材を駆使して作られている金物である。その歴史を古代から1950年代まで史料を駆使して丹念に描いた本書は、現在でも手に取るべき一級の産業史となっている。
目次
【目次】序説 古代篇 1、金物生産された三神╱2、天目、金山 山二神の遺業╱3、菅田 首の南下及東進╱4、百濟王子惠の日本亡命╱5、丹生山明要寺の由来╱6、童男行者の高男建立╱7、疑問の人法道仙人╱8、美嚢郡と法道╱9、法道の東播 大巡錫╱ほか 近世篇 1、三木町の代官制度╱2、その頃三木町の様相╱3、再生した三木町の諸職╱4、出稼人の發生と消滅╱5、傀儡師の一考察╱6、野道具鍛冶の意義╱7、鍛冶の大勃興╱8、加東郡鍛冶の発祥╱9、鍛治組合の組織╱10、金物問屋の接頭╱11、海上輸送の困難╱12、双物一手御買上げ事件╱13、生産高とその価格╱14、冥加銀札にて納税╱15、幕末頃の大勢 現代篇 1、明治初期の形成╱2、金物問屋の発展╱3、三木金物組合商会の創立╱4、一路発展へ前身╱5、空前の大輸出前期╱6、全盛を極めた三木輸出貿易╱7、噂の種あの人この人╱8、終戦後の立直態勢╱9、海外市場へ積極的活動╱10、播州金属興業振興対策╱11、三木金物大見本市開かる╱12、経済安定原則に則して╱13、新殖産奨励制度╱14、三木金物取引改善申合╱15、輸出に協定価格制╱ほか