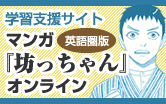HOME > 書籍検索 > 戦後復興期主要産業の実態 全14巻
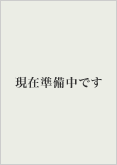
戦後復興期主要産業の実態 全14巻
揃定価155,100円(揃本体141,000円)
ISBN 978-4-8433-2683-1 C3333
A5判上製
刊行年月 2007年09月
本書の内容
ドッジ・ラインが実施された昭和24年から同29年まで、主要産業部門20件に関する詳細動向記録。
高度経済成長の基盤を築いた時期を活写する貴重文献。
監修のことば 中村青志(東京経済大学経営学部准教授) 昭和20年代初めの日本経済は、まず財閥解体、農地改革、労働改革などの戦後経済改革が進められる一方で、敗戦後の極度の物資不足やインフレーションの進行により、国民生活は著しく疲弊していた。そこで、資材と資金を石炭と鉄鋼などの重要産業部門に集中する傾斜生産方式が採用され、復興金融金庫融資と価格調整補給金のもとで産業活動を軌道に乗せ、復興をめざした。ついで、経済安定9原則を打ち出した昭和24年に始まるドッジ・ラインのもとで、復興金融金庫の貸付は停止され、価格調整補給金も削減されて、日本経済は不況に直面する。しかし、昭和25年に勃発した朝鮮戦争のもとで、繊維と金属を中心とする特需景気で息を吹き返し、鉱工業生産が戦前の水準に回復した。昭和20年代後半には、基礎産業に国家資金が積極的に投入され、電力、造船、鉄鋼などの産業部門が設備投資を活発に進め、昭和30年に入ると、高度経済成長に突入する。
このように、昭和20年代のわが国の産業は、敗戦後の荒廃状態から曲折を経ながら復興を実現し、高度経済成長の基盤を築いていった時期である。産業レベルでも、企業活動レベルでも、その動向は興味深い。しかしながら、戦後の混乱の時期であったため、各産業の動向を示す統計その他の資料は、必ずしも体系的に整備されていない。したがって、この時期を対象とする研究の際には、データや資料不足から不便を感じる面も多かった。
そうしたなかで、通商産業省通商企業局が、ドッジ・ラインが実施された昭和24年以降、主要産業の動向を詳細に調査した報告書を作成していた。当初は『経済安定計画実施後の主要業種の実態』のタイトルで発表され、のちに『わが国主要産業の実態』と名称を変えて、昭和30年まで15回刊行された。最初に刊行された第一編では、石炭、コークス、電力、電気銅、鉄鋼、ソーダ、染料、化学肥料、炭鉱機械、電気機械工業、電気通信機械、自転車、自動車、軸受、綿紡、人絹糸、セメント、紙パルプ、時計、光学機械の20の産業部門がとりあげられ、それぞれにつき、需給の状況、価格補給金削減の影響、合理化の進展状況などが記述されている。その後、対象としてとりあげる産業には若干の出入りがあり、各産業に関する調査対象事項も、年次によって変わるが、狭い意味での生産の状況に限定せず、雇用の状況、産業金融の動向まで広くとりあげており、昭和20年代半ば以降の産業動向に関して、この調査報告書がカバーする範囲は広い。今回、復刊される本書は、昭和20年代のわが国の経済、産業、企業経営の研究にとって必須の基礎資料であり、図書館等においても欠かすことができないものである。
【本書の特色】
●戦後復興期の主要産業データを詳細に記す
ドッジ・ラインが実施された昭和24年以降主要産業の動向を詳細に調査した報告書。
●日本の約20業種を網羅
石炭、コークス、電力、電気銅、鉄鋼、ソーダ、染料、化学肥料、炭鉱機械、電気機械工業、電気通信機器など。
●数少ない戦後復興期の産業別データ集
戦後混乱の時期のため、類似の統計はほとんど存在せず、極めて資料価値が高い。
●広範囲の産業動向をカバー
生産の状況に限定せず、雇用の状況、産業金融の動向まで広くとりあげており、昭和20年代半ば以降の産業動向に関して、本報告書がカバーする範囲は広い。