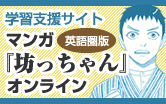HOME > 書籍検索 > いさな叢書1 網野史学の越え方―新しい歴史像を求めて―
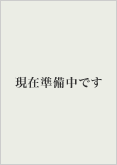
いさな叢書1 網野史学の越え方―新しい歴史像を求めて―
定価1,430円(本体1,300円)
ISBN 978-4-8433-0918-6 C3021
A5判・カバー装
刊行年月 2003年05月
※品切れ
本書の内容
グランド・セオリーに背を向けた現代になおも歴史学の正統な居場所を求める。
次代の歴史学構築のために網野史学の歴史的位置づけを試みた白熱のシンポジウムの全容
「網野史学の越え方」刊行の辞 小路田泰直
最近の歴史学の潮流で私が気になるのは、歴史を、それを書いたり、読んだり、記憶したりする、受け取り手の主観に左右されることの多い物語としてとらえる発想が広がりすぎて、歴史そのものの発展を問題にしようとする人が極端に減少してきていることである。人が何のために歴史を書いたり読んだりするかということについては、多くの人が関心をいだくが、人が書いたり読んだりしている対象である、歴史そのものに内在する発展の法則や、あるいは変化の必然については、ほとんどの人が関心を示さない。そのことが気になる。
その客観的な歴史の法則や必然といったものが、誰かの主観を通してしか認識されえないから、客観的な形で認識されることはありえないということと、それが客観的に存在しないということは違う。しかるに、歴史=物語論に流れるあまり、歴史そのものに内在する法則や必然などありえないと――あるかないかわからないというのならわかるが――端から決めてかかり、歴史の描き手の主観だけを問題にする。そして自らの隠し持っている勧善懲悪の座標の上に、その対象化した主観をのせて、断罪したり共感したりする。そうしたクローチェばりの「現代史」だけが隆盛を極める現在の歴史学界の風潮に、私はこのごろ少し違和感を感じ始めている。
そしてつい思ってしまう。そんなことばかりしているから、結局、一つの流れをもった歴史を書けといわれたとき、歴史が書けなくなってしまうのだと。歴史家が歴史教科書のようなものを書くと、必ず知識詰め込み型の――流れを追うことにさほど意味が感じられないような――教科書になってしまう現状を見れば、私のいわんとしていることがわかっていただけると思う。
あるいは、同じ歴史=物語論を根拠に、だから歴史は民族の誇りを培養するための物語でなくてはならないと語る想定外の人たち(例えば新しい歴史教科書をつくる会の人たち)が立ち現われると、たちまち混乱に陥り、批判の矛先を鈍らせてしまうのだと。
しかし歴史はやはり演繹の学ではなく、経験の学である。歴史それ自体の中に内在する、発展の法則なり、変化の必然を問題にしないのであれば、存在する価値がない。単に過去におきた出来事を素材に、好き放題の物語を書くことが歴史を描くことなのであれば、歴史にフィクション以上の価値はない。
そこで、マルクス主義歴史学が歴史学の表舞台から姿を消してから約20年、久方ぶりに、日本史の全体を貫く発展の法則(グランド・セオリー)とは何か、発展という言葉に違和感があるのなら変化の必然とは何かといったことについて、議論を交えてみたいと思って企画したのが、この元になった「網野史学の越え方―新しい中世史像を求めて―」と題するシンポジウム(2002年一1月3日、於奈良女子大学)である。その意味では、本書は、今風でない、大時代がかった問題関心を未だ内に秘めた者どもの討論の記録である。
ではなぜ「網野史学」を討論の素材に選んだのか。理由は簡単である。それが、マルクス主義歴史学後のこの20年間、この国の歴史学に最も大きな影響を及ぼした歴史学説の一つだったからである。それをとりあげることが、今の時点では、何がいったいグランド・セオリーなのかといったことを考えるのに、最もふさわしい出発点を我々に与えてくれるものと予想させられるからである。
目前にある障壁は乗り越えて前に進みたい。何か新しい知の段階に進もうとする時、古いものは、批判するのではなく、もう古いという理由で投げ捨てていくのが、この国の知のルールだが、そのルールにのりたくなかったからである。
(後略)
●主な内容
【報 告】
・「網野史学」と中世国家の理解 桜井 英治
・網野史学の問題系列 小関 素明
・元寇・倭寇・日本国王ノート
― 網野史学における一四世紀理解をめぐって ―
海津 一朗
・網野史学と古代認識 ―関係・所有・国家―
西谷地晴美
・政治と救済
― 国土観変遷の歴史的意味について ―
森 由紀恵
・網野史学の越え方について
― 現代末法思想考 ― 小路田泰直
【全体討論】
報告者 桜井 英治
小関 素明
海津 一朗
西谷地晴美
森 由紀恵
小路田泰直
司 会 西村さとみ
討論における発言者 布川 弘
大村 拓生